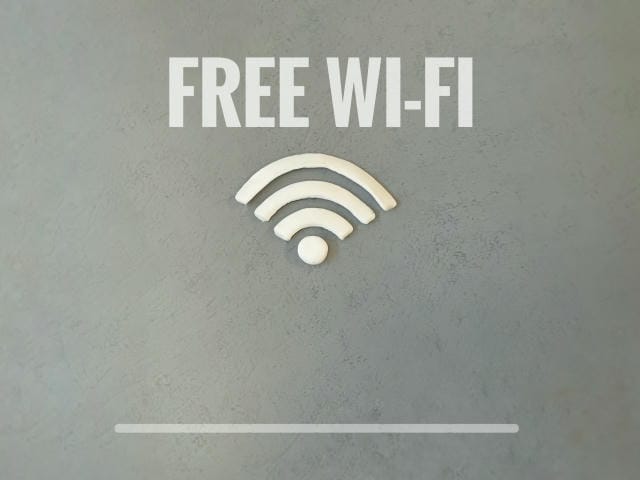インターネットの発展によって、さまざまなオンラインサービスが社会や日常生活の中へ浸透している。しかしその発展に伴い、大きなリスクの一つとして意識されているのが分散型サービス妨害攻撃である。大量の端末を悪用し、特定のサーバーへ対して大量の通信やリクエストを強制的に送り込むことでネットワークやサービスを機能不全に陥らせるこの攻撃手法は、多種多様なサービスへ脅威を与えてきた。本来、サーバーは全世界の利用者へ向けて安定したサービスを提供するため様々な処理能力や容量を備えている。たとえばアクセスの集中が頻繁に起こる業界のウェブサイトであれば、想定される負荷を十分に見積もったシステム設計がなされる。
しかし大量の端末によってサーバーに集中攻撃が仕掛けられた場合、一時的な要求数が通常時の何倍、何十倍にも拡大する。これによりサーバーは処理能力を超えたリクエストを捌ききれなくなり、結果として正規の利用者がサービスを利用できなくなる事態が発生する。このとき利用される端末は多岐にわたり、必ずしも攻撃者自身が管理しているパソコンに限定されるわけではない。不正ソフトウェアにより遠隔操作されることになった一般家庭のパソコン、さらには近年インターネットに接続され始めた様々な機器までが攻撃の踏み台に利用されてしまうこともある。特定の個人が気を付けていても十分な対策をしていない端末が世界中に点在しているため、攻撃者にとってその“兵力”を確保すること自体は容易になってきている。
実際に分散型サービス妨害攻撃が仕掛けられると、ターゲットとなったサーバーやネットワークだけが被害を受けるわけではない。攻撃の発信源となる端末群に加え、その端末が所属するネットワークにも大きな負担がかかる。結果的に攻撃とは無関係な利用者まで通信速度の低下や接続の不安定さといった影響を受けてしまう例も多数報告されている。攻撃の種類としては、単純な大量リクエスト送信だけでなく、通信プロトコルの脆弱性やサーバー側の設計上の隙間を狙った複雑なものもある。状況ごとに攻撃の手口が変化するため、これに対抗するための対策も単一のものだけで対応できなくなってきている。
特に最新の攻撃手法は小さなデータ通信を大量に送信するタイプなど多様化しており、システム管理者やセキュリティ担当者は常に警戒を怠ることができない。たとえば何らかの重要なイベントや発表が控えている場合、そのイベント運営サーバーが攻撃の標的になるケースがある。攻撃によってサーバーがパンクし、本来そのイベントへ参加したかった多くの利用者が受付ページや配信ページにアクセスできなくなってしまう。このため運営側は従来のサーバー管理だけでは不十分となり、普段から分散型サービス妨害攻撃を想定したシミュレーションや訓練、外部ネットワーク監視サービス連携などの備えが必要になってくる。一方で、攻撃の実行自体は専門的な技術がなくても実現可能な場合がある。
誰でも簡単に扱える攻撃用のツールが不正に流通しており、短期間で大規模攻撃を実施できてしまうリスクが多数存在する。しかし中長期的にはこうした攻撃を行う端末を減らす、踏み台にされないように端末管理を厳重にしていくことが被害全体を抑える根本的な解決策の一つとなる。例えば端末のセキュリティ更新をこまめに行い、ウイルス対策ソフトウェアを常に更新した状態に保つことは被害拡大を予防する最良の方法である。また、パスワード管理の徹底や無線通信ルーターのセキュリティ設定変更も効果的だ。サーバーの管理現場においてもどのようなアクセスが想定外のものか即座に検知できる監視システムを導入し、新たな攻撃の兆候を早期に察知する努力が求められている。
困難な課題にはなっているものの、端末ごとの対策とサーバー側の防御の二重の備えを強化することで、被害の規模や範囲を着実に抑えていくことは可能である。さらに通信の根本となるインターネット全体での協力体制・情報連携も徐々に進展している。安全なデジタル社会を維持していくためには、すべての端末利用者とサービス提供者がそれぞれの立場で分散型サービス妨害攻撃対策への関心と備えを持つことが不可欠である。被害が具体化する前から備えを進めることによって、インターネットという社会基盤の信頼性は今後も守られるだろう。インターネットの普及に伴い、さまざまなオンラインサービスが私たちの日常に欠かせない存在となる一方で、分散型サービス妨害攻撃(DDoS)の危険性が増しています。
DDoS攻撃は、大量の端末を悪用して特定サーバーに膨大なリクエストや通信を送りつけ、サービスを一時的に停止状態に追い込むものです。攻撃には犯罪者が直接操作する端末だけでなく、ウイルスによって遠隔操作された家庭用パソコンやIoT機器まで幅広く利用されており、世界中の管理が不十分な機器が攻撃の踏み台とされる現状があります。DDoS攻撃の影響はターゲットのサーバーにとどまらず、発信元となった端末やそのネットワークにまで波及し、無関係な利用者の回線速度低下など二次的被害も引き起こします。攻撃手法自体も多様化・高度化しており、単純なリクエスト洪水だけでなく通信プロトコルの脆弱性を突くケースも増えています。そのため、管理者は24時間体制で監視や早期検知を行い、サーバー負荷分散や外部の専門業者との連携といった多層防御が必要となっています。
個人端末レベルでも、セキュリティ更新やパスワード管理、ルーターの設定強化、ウイルス対策の徹底が重要です。技術的な知識がなくても攻撃ツールが流通しているため誰もが加害者にも被害者にもなり得る現代、インターネットの信頼性を保ち安全な社会を維持するには、全ての利用者とサービス提供者が自分事として対策を講じていくことが求められています。DDoS攻撃のことならこちら